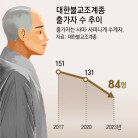「氷点」の作家である三浦綾子は、韓国の読者にもおなじみの名前。最近、彼女の夫である三浦光世が妻に対する深く、献身的な愛を記録した本が出た。
三浦光世が書いた「妻とともに生きる」(東映メディア)には、二人の初めての出会いから30年あまりの歳月をいっしょに夫婦として暮らし、そばで感じた妻の話がありのままに綴られている。暖かいぬくもりとほのかな香りがページをめくるほどに染み出るこの本は、厳しい世の中でぎすぎすした暮らしをしている現代人の胸に響く。
光世は、綾子にはじめて会った1955年6月18日を「一生忘れられないあの日」として覚えている。当時綾子は、肺結核が発病して9年、脊椎慢性炎症に苦しんで3年になった状態であったため、ほとんど寝たきり同様だった。3度目に会った後、光世はこのように祈った。
「神様、私の生命を綾子に与えてもいいから、どうか病気が治るようにしてください」
新婚生活は、貧しかったものの幸せだった。光世は、一間の部屋だったが本当に「狭苦しいながらも幸せな家」だったと回想している。こじんまりとした空間だったが、家には本物の詩があった。
雑貨店「三浦商店」を営むかたわら小説家の夢を育てていた綾子は、1964年朝日新聞が主催した小説の公募に「氷点」が当選した後、店を閉じて専業作家の道に足を踏み入れた。光世は、相次ぐ原稿の執筆と講演で忙しい綾子を手伝うため仕事をやめる。光世は「夫がご飯を作ろうが、お茶を入れようが、お互いのためになれば別にかまわない」と思った。
綾子の健康が悪くなった1966年以後からは、口述するのを書き取り、作品活動を手伝った。光世は、綾子が書いた小説やエッセーの内容について一切自分の意見を口にしたことがないと話している。
光世は、結婚式の途中、「わたしたち二人は、同時に死ぬのではないか」という思いがふとしたと話している。綾子は1999年に先に亡くなったが、それでもその二人は「一心同体」に違いない。
趙梨榮 lycho@donga.com