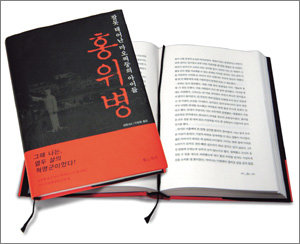
文化大革命(文革)は中国人たちの意識の中に『ナイトメア』や『13日の金曜日』のように数多く繰り返し製作されたホラームービーだ。紅衛兵はそのホラームービーの殺人鬼であるプレディーやジェイスンだ。いや、もう少し正確に言えば悪霊に憑かれたおもちゃ人形のチォキだ。
韓国の現代史さえまともに分からない人々に他国の現代史を説明するのにこれよりいい比喩はないかも知れない。あまりに断片的な説明だと?「文革」と「紅衛兵」はすでにその歴史的実体を離れて、「集団狂気」や「物知らずの親衛勢力」を意味する文学的修辞になったのではないか。
しかし、今年米国でノンフィクションで出刊された『紅衛兵』は、文革が悲鳴に満ちた虚構ではなく悲鳴さえ飲み込まなければならない現実だったことを、紅衛兵はその悲劇の加害者だっただけでなく、犠牲者だったことをありありと証言する。
著者沈凡(50)は米国中部の小さな大学に英文科教授として在職している。現在の経歴からすれば、彼と紅衛兵の関連性がすぐ思い浮かばない。しかし、彼の名前には革命の烙印が赤く押されている。
「私のお爺さんとお婆さんは清王朝、そして外国勢力に抵抗した革命家だった。親も日本と国民党に対立して戦う共産革命家の人生を送った。… そして初の子供の名前は革命家に相応しい『凡』の字にすると宣言した。その名前は数百万の労働者のうち平凡な一人を意味した。」
そのように革命の血が流れる家で生まれた彼は、1966年5月17日「人民日報」に掲載された「紅衛兵に命ずる、あちこちに隠れている敵を捜し出して処断しろ」と言う毛沢東の命令を神さまの啓示のように受け入れる12歳の紅小鬼(幼い紅衛兵)だった。軍の将校だった父親、党幹部だった母親と一緒に北京に暮した彼はあらゆる書籍を燃やして、学校教師と指導級人士に残忍なリンチを加えながら快感を感じた。彼にとって文革は楽しいゲームだった。親も、教師も、誰もがそのゲームを邪魔することができなかった。
教師と授業が消えた学校で彼らは「万里の長城の闘争組」だの「恐れぬ赤い革命軍」だのというサークルさえ結成すれば、直ちに教室を一つずつ獲得することができた。「隠れている敵」は毛沢東を除いたあらゆる「権威」の持ち主だった。その権威は知識と財産、権力を取り揃えた社会エリートたちだった。
数万人の紅衛兵がサッカー場に集結して軍の将星や北京市長をほとんど裸姿にしてあらゆる屈辱と暴力を加えながら熱狂する場面を読んでいたら「広場の拷問」が「密室の拷問」をしのぐ可能性があることを実感するようになる。また数百万人の紅衛兵が天安門広場に集まって一つの点に過ぎない毛沢東の出現に集団ヒステリー症状を見せて気絶する場面では集団催眠の怖さに身の毛がよだつ。
しかし、文革はただ混乱のための混乱だったし、紅衛兵は権力闘争の手段に過ぎなかった。絶えず「隠れている敵」を探し回った紅衛兵たちは生きた人のお腹を割って醤油を降り注ぐ狂気に捕らわれて、結局はお互いを殺して死ぬ。
この本の本当の魅力は紅衛兵の実際を告発する前半部ではなく、そういう生を覆していく後半部にある。2年間の紅小鬼生活が終わった後、彼は奥地に行って労働者、農民として生きていきなさいという「偉いリーダー」の教示に従って、親下を離れて、数千km離れた荒れ地で無知の農民として4年、そしてまた原因不明の自殺者が続出する工場労働者として6年を生きる。その間彼は「革命の刀」から「革命に向けた刀」として鍛えられる。
彼が民衆の中で学んだのは革命性ではなかった。彼らの元気な楽天性と老会な處世術だった。彼はこれを武器に文革によって忘れてしまった歳月を取り戻すための復讐に出る。彼は昼間を仕事をし、夜は勉強をして知識を積む一方、おせじと買収、そして偽りで愚かな党の官僚たちを利用して大学生になり、結局1984年米国留学とともに彼らと別れを告げたからだ。
この本は革命の虚構性を暴露する強烈なメッセージに劣らず小説に匹敵する吸引力を持っている。紅小鬼時代の著者が悽絶に破壊したが、一生「救援の女人」になったリリンとの悲劇的な愛は、映画『ドクトルジバゴ』を連想させるほど劇的だ。また自らを幾多の冒険の末に玉皇上帝に向けて反旗をあげた孫悟空に比喩する著者の滑稽さが見事だ。原題は『Gang of One』(2004年)。
權宰賢 confetti@donga.com







