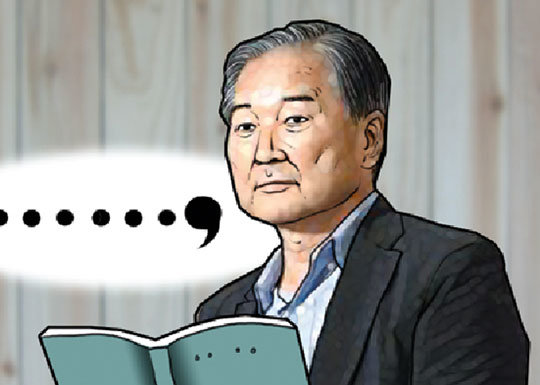
文章にはピリオドが打たれるが、それを伝える感情は、ピリオドを拒否することがある。不在対象に向けた懐かしさの感情は、なおさらそうである。馬鍾基(マ・ジョンギ)詩人の「冬の墓地」はピリオドを拒否する懐かしさに関する詩である。
「血縁の荒涼とした墓地に立つと」という言葉で始まる詩で変わったことは、他の行では打たれていたピリオドが、最後の行ではこっそりと消えることである。「空がより低く降りてきて、私たちは手を握る・/いつの間にか雪が止まり、風が凪いで私たちは、」。正常な詩なら、このような不完全な形では終わらなかったり、終わってもコンマの代わりにピリオドが打たれる。ピリオドのところに入ったコンマ、これが私たちを詩人の傷の中に案内する。
彼が詩の中で語る「血縁」とは、この世を去った弟だ。彼が複数の弔詩と散文で吐露したことから見て、彼と弟はそこまで仲がいいだろうかと思われるほど、友愛が深かった間柄だった。その弟が見知らぬ国に来て、近所の人として生き、黒人強盗の手によって死んだ。衝撃も並大抵のものではなかった。詩人が感じる悲しみと哀悼の感情に、ピリオドが打たれるはずがなかった。最後の詩行「いつの間にか雪が止まり、風が凪いで私たちは、」で、ピリオドのところにコンマが入ったのはそのためだった。詩人の言葉を引用すれば、それは「いつか死んでも弟との関係を続けたい」という気持ちから出たものだった。懐かさのコンマといったところだろうか。
そのコンマをさらに美しくさせるものは、憎悪と復讐心の不在だ。詩人は犯人に死刑判決が下されたことを知って、弟の息子、つまり甥と一緒に死刑執行に反対する意見書を米裁判所に出した。大げさに人道主義を実践するためではなかった。人を殺すことは人ではなく、「神の権限だ」と信じていたからだった。彼の役目は、憎しみや復讐ではなく、コンマで続けていく懐かしさの感情であり、人生が終われば、懐かしさの対象である弟に会えるという希望だった。だからピリオドのところに入ったコンマは、懐かしさと希望のコンマだった。







