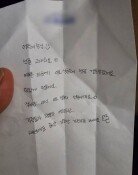毎年春になると、野山への花見に忙しい私を、妻は「花が好きな男」「女のような男」と呼ぶ。生物学を専攻した私は花が好きで、20代前半、英国に住んでいたときは王室の庭師として働いてみたくて志願したこともある。外国人なのでチャンスが来なかった。生活の問題を解決するためにホテルで皿洗いとして就職したキッチンで、シェフの道を歩むことになった。
1980年ごろ、ペルーのマチュ・ピチュの谷に咲いた赤いグラジオラスをおいしく食べていたラマ二頭に出会った。不思議なことにつぼみだけを選んで食べた。しばらく見守っていて、知りたくなり、私もつぼみを取って食べてみた。何の味もなかった。子供の頃、赤いハイビスカスはつぼみごと取って、口にして吸うと、甘い味が感じられた。もちろんチューチュー吸うと、お腹がすいていた記憶も思い出すが。あの時も今も道端にいっぱい咲いていて、誰でも沖縄に行けば簡単に見ることができる。最近は乾燥させたものが、お茶として作られ、販売される。甘酸っぱいお茶を氷と一緒に浮かべて飲む「抗酸化茶」として人気が高い。
ニューヨークのフレンチレストランで働くとき、レストランのオーナーから、自分の故郷であるプロヴァンスから持ってきたと言われ、料理に応用するようにと、ラベンダーをもらったことがあった。米粒のような外観と紫、濃い香りを持っていた。ホイップクリームを沸かした後、ラベンダーの花を浸して香りが出るようにしておき、蜂蜜と混ぜてアイスクリームを作ってはシロップに漬けて乾燥させたラベンダーの花つぼみで飾って出した。
植物学者・ルーサー・バーバンクは、「花は人の心を動かして幸せを感じさせる。見ることを超えて食べ物になり、薬になって魂まで癒す」という言葉を残した。客の反応がぴったりそうだったようだ。あの日から定番メニューになった。
1992年のメキシコ映画「赤い薔薇ソースの伝説」の主人公「ティタ」は、ウズラにバラの葉を入れてすりおろして作ったソースを添えて、彼女の愛するペドロに渡す。スタミナを高めるレシピで、食卓で一緒に食べたすべての人たちを興奮させるシーンが演出される。
食用の花の歴史は、紀元前140年に遡る。ローズウォーター、オレンジの花の香水は、最近も中東地域の家庭で多く使われる。クロッカスの雄しべを乾燥させて料理に使うサフラン、ビールの主材料であるホープも花だ。韓国でもたくさん食べるブロッコリー、カリフラワーも、野菜だと思うが、実は花を食べるのだ。
私は毎年この時期になると、農作業に忙しい。食用の花と香りのあるハーブを中心に育てるためだ。キンレンカは美しい姿と違って、スパイシーな味が感じられ、花や葉をサラダの材料として使う。カボチャも欠かさない。カボチャよりは花がもっと好きで、イタリア流に中を詰めて揚げたり、サラダにするなど、さまざまな形で調理して食べる。
20世紀に入ってから、農薬の拡散によって食用の花はたくさん消えた。高級レストランで使うのは、有機栽培されて高価だが、家で育てるなら話は違う。小さな鉢でも、自然が与える最高の贈り物である花を見て食べて飲んでみよう。幸せをいっぱい感じることができるだろう。