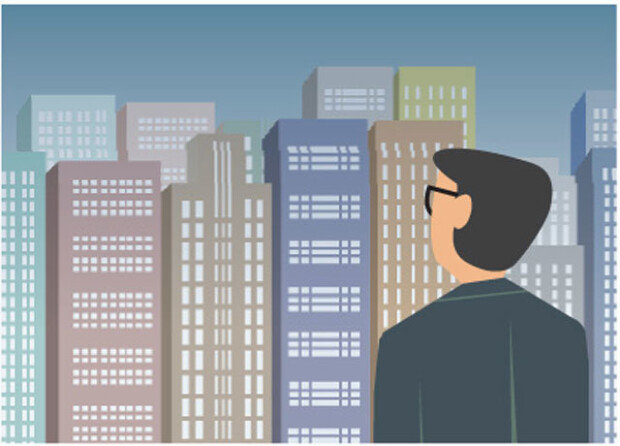
大きく見れば、懐疑や冷笑は関心の逆説的表現だ。関心がなければ、敢えて懐疑的だったり冷笑的になったりする必要もないからだ。「建築社会学」という副題のついたハム・ソンホ詩人の連作詩から感じられる懐疑と冷笑もそうだ。
彼の目に映ったソウルは、見かけ倒しの輸入完成品だ。「ソウルは光を放つ-誰がこんなに一晩中ソウルを磨いておいたのか/キラキラしています。輸入完成品のソウル」。ソウルが全面的な輸入品とはどういう意味だろう。「巨大な欲望の城塞」のように見える建築物、「ネオンできらめく広告塔と教会の尖塔」「バベルの塔のように高くなるだけの金融会社の社屋」を含め、すべての建築物が詩人の目にはそう見えるということだ。しかし、輸入品というのは自分のものがないという言葉であり、自分のものがないという言葉は、哲学も歴史意識も美学的論理も欠けているということだ。詩人にとって、そのような建築物は建築ではなくセットだ。必要なら立てて、必要なら壊すセット。あるいは彼が他の文章で繰り返して引用したハイデッガーの言葉通り「魂のないコンテナ」。これよりもっと懐疑的で冷笑的な見方があるだろうか。
詩人はなぜそんなに批判的なのか。建築と関連して、伝統の断絶、歴史意識の不在を語りたいからだ。美学的原理の不在、共同体が追求する価値の不在について話したかったからだ。建築物がそのような不在を証言しているということだ。もちろん、これは非常に辛い評価であり、誇張された面もなくはない。しかし、歴史意識と美学的論理のない建築家は、資本に振り回される技能工や知識技術者にすぎないという考えには背を向けられない。建築家を兼ねる詩人でなければ、誰が韓国の近代建築を対象にこれほど辛らつな詩を書くことができるだろうか。しかし、これは建築だけのことではない。政治、経済、教育、芸術を含むすべての分野の問題だろう。13編の詩から感じられる懐疑と冷笑、揶揄の尖った部分が、小さくは建築、大きくは全般的な文化に対する深い愛情と省察の産物である理由がここにある。
文学評論家・全北(チョンブク)大学碩座教授







