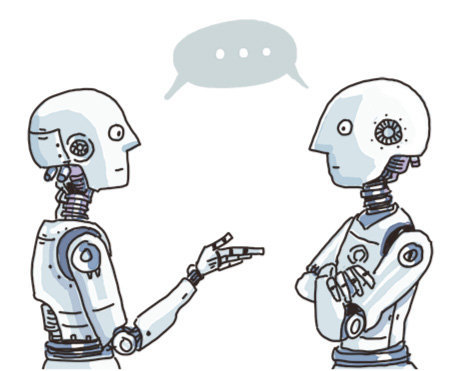
「最初から生まれてこないことが最善だと考える。生まれてこなかったら、何の苦痛もなかったのだから」。旧約聖書のヨブの絶望の中での絶叫に似た、作家金英夏(キム・ヨンハ)の小説『別れのあいさつ』に出てくる言葉だ。話者はこのように言い返す。「生きて感じる喜びはないですか」。するとこのような返事が返ってくる。「それによって苦痛の害悪が相殺されるでしょうか」
興味深いこの対話は、人間と似た身体を持つロボットであるヒューマノイドが交わす対話だ。一方は生まれてこないことが最善と言い、もう一方は、それでもどこかに喜びがあると言う。この対話に遺伝子複製で生まれたクローンが割り込む。「意識と十分な知能を持っている存在なら、この世の中に溢れる不必要な苦痛を減らす義務がある」。どうせ生まれたのだから、他の存在の苦痛を減らして生きようということだ。彼が見る世の中は美しい。彼は冬の湖を見て話す。「ただ氷と水にすぎないが、なぜこれがこのように胸が迫るように美しいのだろうか。水というのは水素と酸素の分子が結合した物質にすぎないのに。ところでなぜ私たちはこのようなものを美しく感じるようにできているのか」。苦痛で満たされた世の中だが、彼はその美しさを少しの間見ることだけでも十分に幸せだと感じる。
それでも彼らは、「この地球で不必要な苦痛を圧倒的に生産する存在がまさに人間」ということに同意する。生まれてこないことが最善という結論がここから出てくる。悲しい帰納法だ。彼らの考えは、作家が明らかにしたように、倫理学者デイヴィッド・ベネターの著書『生まれてこないほうがよかった』に出てくる考えを繰り返す。小説はそのような考えを中心に黙示録的な理由を展開する。少し暗くて悲しく、虚しい話だ。少なくともそれを相殺するのは、そのような理由を展開する作家の目だ。人間だけでなく苦痛の中のすべての存在に向かった憐憫の目。その一方で感動させる世の中の美しさを逃さない目だ。







