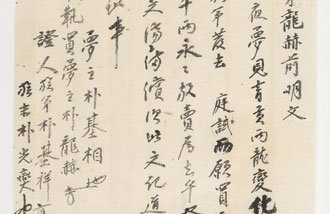欣然と官職を辞し、故郷の田園に戻った陶淵明。農作業も行い、近所の農民たちとも気さくに過ごすなど、人生のゆとりを満喫しているように見えた。しかし、どうして糧食を請うまでに至ったのか。「困窮の節を懐き/飢寒はもう十分というほど味わった」(「飲酒」其十六)。避けられない選択だった。隠者の尊厳と高潔さを崩壊させる貧しい境遇を詩にする心情はどれほど苦しかったことか。相手に恩返しする道がないことを認めなければならず、それゆえ詩人は漢の高祖、劉邦の側近である韓信の話を持ち出す。韓信が飢えた時、洗濯場のおばさんが数日間食事を提供し、後日、韓信がその恩を充分に返したという話だ。「あの世に行ってでも必ず返す」という決意は、行き詰まった境遇の詩人の唯一の解決策であり、自らへの慰めでもあったのだろう。しかし、陶淵明の忠実な後継者である王維でさえも、この詩については「世に背を向け、大事を忘れ、小事に固執した」ためだと不満を吐露した。