
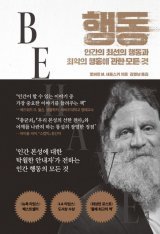
米国の南北戦争の最も激しい激戦地であったゲティスバーグの戦いでは、単発式マスケット銃が2万7千丁近く回収されたが、そのうち約2万4千丁は一度も発射されていない状態だったという。阿鼻叫喚の戦場で、兵士のほとんどは銃を撃つどころか、負傷者の世話をしたり、命令を叫んだり、逃げ出したり、茫然と徘徊したりしたということだ。「人間は近距離で他人に重傷を負わせることを強く嫌う性質がある」という。だから個人を撃つよりも、集団に手榴弾を投げる方が簡単だ。遠く離れたとはいえ、映像で相手を観察しなければならないドローン攻撃も同様だ。ドローンでアフガニスタンの敵を監視して攻撃して殺した米軍兵士たちは、多くが心的外傷後ストレス障害(PTSD)になった。
人間は戦争をして数千万人を殺すが、同時に顔を合わせる敵軍と容易に絆を感じる存在でもある。南北戦争でも、兵士たちは敵と仲良くなり、物々交換をしたり、戦闘前の夜に共同で礼拝を開いたりした。第1次世界大戦当時、塹壕戦で自然に「クリスマス休戦」があったことはよく知られている。
いったい人間はなぜこんなに矛盾した行動をするのだろうか。副題「人間の最善の行動と最悪の行動に関するすべて」のように、人間の暴力性と利他性という両面、道徳性と自由意志、部族主義と外国人排斥などについて「生物学と心理学、文化的側面を総合して」扱った本だ。米スタンフォード大学の教授で世界的に著名な神経科学者である著者が執筆に10年以上かかった力作で、引用した研究の出典を明らかにした後註だけで薄い本一冊分になる。
前半は「特定の行動はなぜ起こったのか」という問いかけのもと、時間を遡って章を分けて説明している。行動が起こる「1秒前」は脳神経科学の時間帯だ。脳の扁桃体は恐怖、不安、攻撃性に関係しており、制御を担当する額葉(前頭葉)の外皮が損傷すると、人は衝動を抑制できなくなる。脳で感情を担当する部位と認知を担当する部位が別々に働くこともある。「5人を救うために1人を殺してもいいのか」といういわゆる「トロッコ問題」で、回答者が「直接1人を線路の上に押さなければならない」状況を提示すると、脳の感情に関連する領域が共に活性化したが、「ただレバーを引けばいい」という状況では認知領域だけが活性化した。
行動する「数秒から数分前」は感覚の時間帯だ。実験によると、私たちの脳は肌の色に非常に敏感だ。誰かの顔写真を10分の1秒もない短い瞬間見せると、人々は何を見たのかさえ確信できない。しかし、写真で見た顔の人種を当てろと言うと、かなりよく当てる。被験者と異なる人種の顔を見せると、扁桃体がよりよく活性化されることもある。これは人間の脳が「私たち」と「彼ら」を瞬時に分けることを意味する。しかし、人間はそこに無条件に支配される存在ではない。著者は、「意識が感知できるほど長く(約0.5秒以上)さらされると、その後、前頭前野が活性化し、扁桃体が静かになる。自らも不快な感情を調節するのだ」と指摘する。
本はこのように「数時間から数日前」のホルモンの話と「数日から数ヵ月前」の神経可塑性を扱った後、青少年期、小児期、胎児期に経験した変化が行動にどのような影響を与えるかを探る。続いて、文化、進化へとテーマを広げていく。著者は、人が誰かを助けることについては、「自転車に乗るのと同じように、長い間身につけた結果、無意識のうちに自動的に飛び出す行動の問題」だという。ウィットに富んだ文章と豊富な事例を通して展開するので、本の厚さに恐れることはない。原題『Behave』。
趙鍾燁 jjj@donga.com







